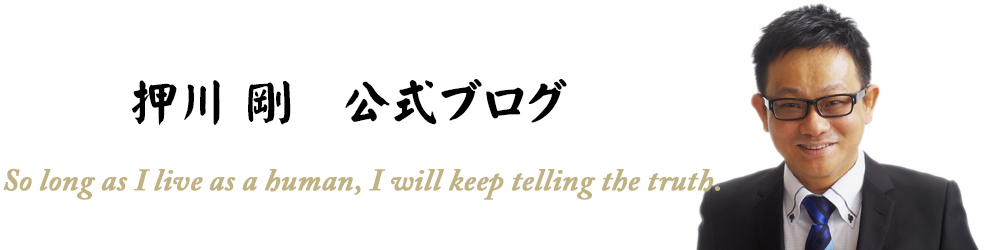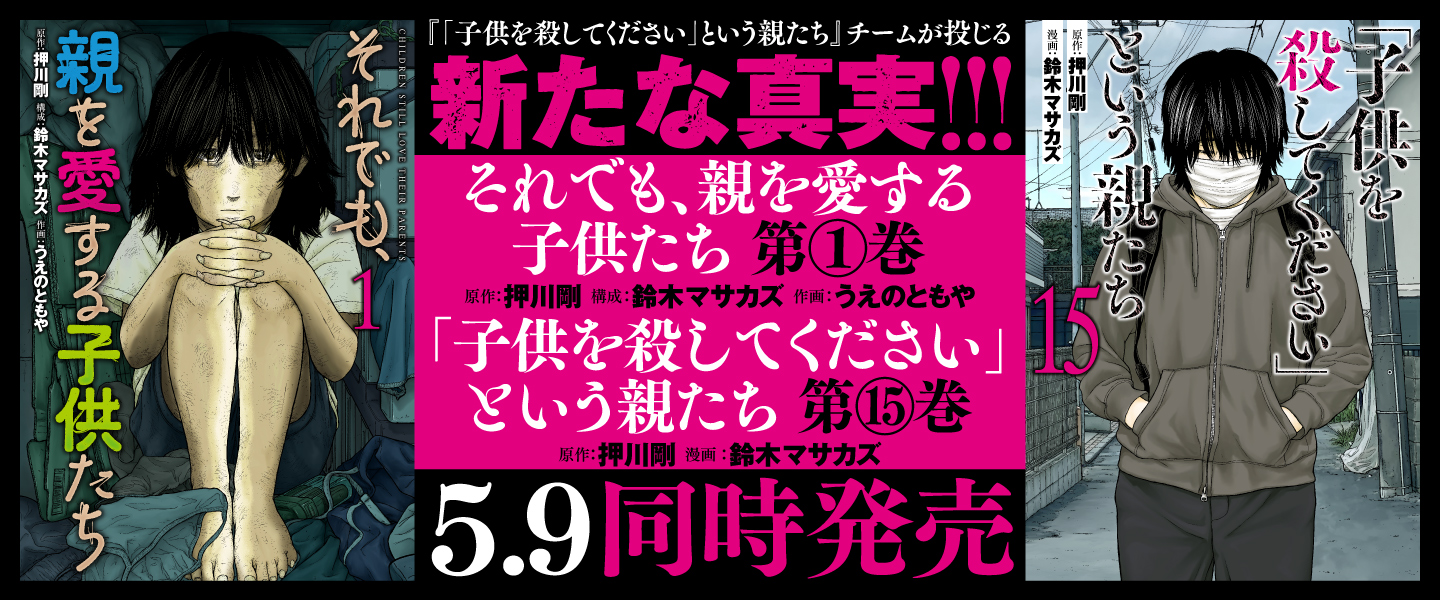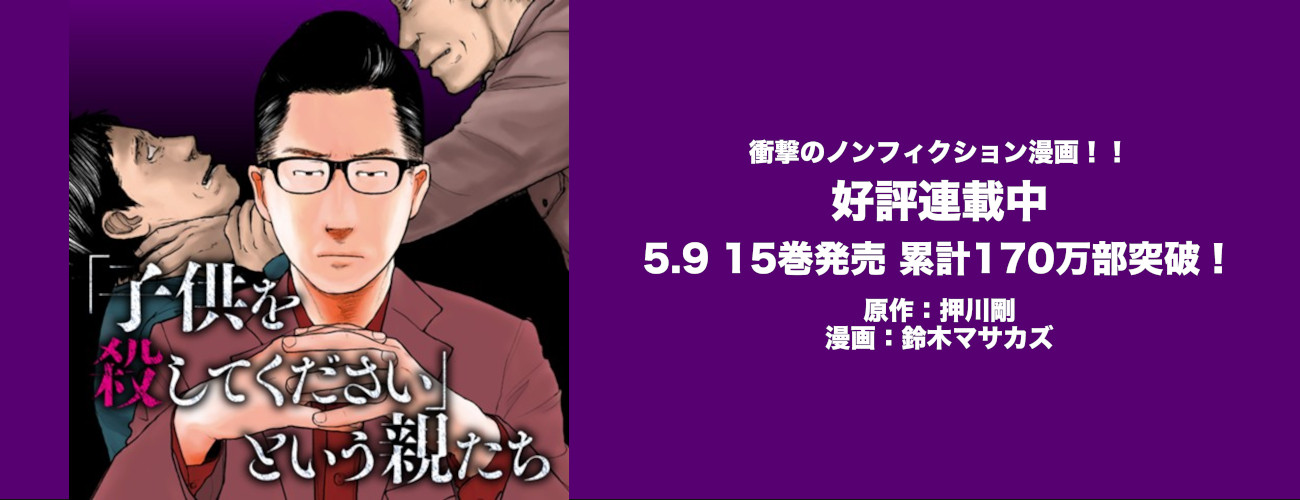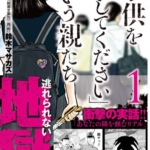
「ひきこもり」診療の世界的第一人者! あの斎藤環教授から、革命的模範回答書賜りました!!
今年の5月8日、世界の斎藤環教授より、毎日新聞経済プレミアに掲載された私へのインタビュー記事(「ひきこもり 自宅を占拠し両親を奴隷化した20代長男」を引用していただき、以下のようなツイートを賜りました!
なんと!同日の世界の斎藤環教授の一連のツイートでは、最後に私のブログを引用していただき、「YES 対話! NO 説得!」というコメントまで賜りました!
そこで私は、弁護士を通じて世界の斎藤環教授に通知書を送達いたし ...

そもそもの話として… 「精神保健福祉法第34条(医療保護入院等のための移送)」
説得による「精神障害者移送サービス」について、暴力的だ、違法行為だと騒いでいる人がいるので、「そもそもの話」をシリーズで説明していく。
そもそも「移送」は、精神保健福祉法に定められている。
以下はその条文である。
(医療保護入院等のための移送)
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障 ...

斎藤環さん、20年近くも姑息なこと「もうやめないや」
ここ最近の私の斎藤さんへの発信について、事情を知らない方だけでなく、長く私を応援してくださっている読者の方からも「押川さん、急にどうしたのですか」「斎藤氏の件に偏りすぎではないですか」とご指摘をいただいている。
ここではっきりさせておくが、私にとっては「急」な話ではない。斎藤さんは私の仕事がマスメディアに取りあげられはじめた十数年前より、インタビューや文字媒体、パブリックの場において、民間の移送会社を敵視し、暴力の行使や拉致監禁による移送をしているかのような発言を繰り返してきた ...

国は今こそ、「ひきこもり」の定義を、より明確にせよ
私が携わっている「ひきこもり」の方々は、精神疾患(疑い含む)があり、適切な治療が必要な状況にありながら、医療につながれていない重度の患者である。それゆえに私には直接、関係のないことであり、私見でもあるのだが、一つだけ確信をもって断言しておこう。
近い将来、オープンダイアローグ・ネットワークジャパンや日本家族研究・家族療法学会のバックアップを得て「社会的ひきこもりの人権を守る会」が正式に発足され、それを支持する政党も ...

毎日新聞経済プレミア「崩壊家族 日本の現場」連載第二回掲載
毎日新聞経済プレミアの連載 「崩壊家族 日本の現場」、8月10日の今日、第二回目が掲載されました。
『息子の精神疾患を30年間隠し続けてきた両親の葛藤』。
ぜひお読みください。
これからお盆の帰省シーズンが始まります。実家に帰省する際には、両親やきょうだいの様子を気にかけてほしいと思います。
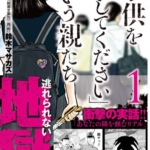
「ひきこもり」診療の世界的第一人者! あの斎藤環教授から超特大【〇〇〇〇〇】お墨付き!!
世界初の社会派漫画、『「子供を殺してください」という親たち 1 (BUNCH COMICS)』コミックス第1巻、本日より発売開始しております。
世界の斎藤環教授より、刊行前からいち早くお目をつけていただき、超特大【フルボッコ】……「読んではいけない漫画」として大推奨を賜りました。(以下、斎藤氏の2017年5月8日ツイッターより引用)
こういう描写が精神障害をスティグマ化する。そこに正義はない。 …
スティグマとは以下の偏見を指 ...
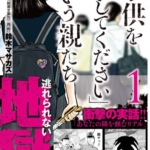
A new release of the world’ first social awareness comic book on mental health in Japan: ”Parents who supplicate ‘Please kill my child’”
The Vol.1 comic of “Parents who supplicate ‘Please kill my child’(「「子供を殺してください」という親たち 1 (BUNCH COMICS)) ”will be launched o ...
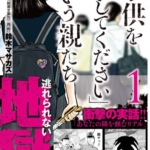
いよいよ明日は、世界初!の社会派コミックスの発売日です!
@バンチwebの『「子供を殺してください」という親たち』の応援コメントページは、
「実吉さん、かわいいね」
「実吉は、押川より超絶にアタマがいい!」
「押川の髪型、アタマの上にチ〇ポのせてるのか?」
…などという応援コメントも入るといいなと思いつつ、実際は、社会派コメントでいっぱいです。さすが読者層の偏差値が高いです。
精神疾患にまつわる家族の問題は、「命」に関 ...

シリーズ 『清く正しい危機管理講座①』
まあまあの数の若い諸君が集まったなあ。それじゃさっそく、第一回目の講座をはじめるぞ。
先週のことだが、●●●●●●●●●医科大学で精神看護学を担当しているというセ・ン・セから、
―――――――――――――――――――
「こんにちは。はじめまして。●●●●と申します 。●●●●●●●●●医科大学で、精神看護学を担当しています。突然のメッセージ、すみません。
実は、精神科救急に関する研究を病院の ...
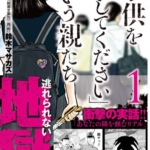
『「子供を殺してください」という親たち』コミックス発売に当たって
8月9日、『「子供を殺してください」という親たち』コミックス第一巻が刊行される。「なぜ今、漫画なのか」については、巻末に渾身のコラムを書いた。ここでは別の角度から俺の思いを伝える。
◇「命」に本籍
俺は「命」に本籍をおいてこの仕事をしている。これまでたくさんの家族の現場を見てきて、適切な治療やケアを受けられずに精神疾患の症状が悪 ...
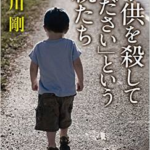
『「子供を殺してください」という親たち』累計7万5千部
『「子供を殺してください」という親たち』が増刷(12刷)され、累計7万5千部となりました。皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。
今後とも精進してまいります。ますますの応援、よろしくお願い申し上げます。
「子供を殺してください」という親たち (新潮文庫)
posted with ヨメレバ押川 剛 新潮社 2015-06-26AmazonKindle楽天ブックス7netこちらもよろしくお願いします。
「子供を殺 ...

相模原障害者施設殺傷事件 植松被告は「招かれざる客」だった
戦後最悪とも言われた凄惨な事件から26日で一年が経った。神奈川県相模原市の障害者施設において、元職員の男性が十九名の入所者を殺害し、二十七名に重軽傷を負わせた、相模原障害者施設殺傷事件である。
テレビ、新聞など報道の大半は、差別やヘイトクライム、共生社会をどう実現するかといったところに焦点が当てられていた。その側面からの考察はもちろん必要だ。だが私は、この事件を教訓として、再発防止の視点から考えを述べたい。

毎日新聞経済プレミア「崩壊家族 日本の現場」連載第一回掲載
先日より告知しておりました、毎日新聞経済プレミアの新連載「崩壊家族 日本の現場」、7月18日の今日、第1回目が掲載されました。
『「ひきこもり10年」30代娘に親はどう対応してきたか』。
ぜひお読みください。

毎日新聞「経済プレミア」連載開始
今月より、毎日新聞「経済プレミア」にてコラムを執筆することになった。第1回目は近日中に掲載予定だ。
これまでに携わってきた事例と、最新のデータをもとに、現代家族の実態を書いていく。
タイトルは「崩壊家族 日本の現場」。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

真実を知る
漫画『「子供を殺してください」という親たち』だが、コミックバンチwebのコメント欄に、ときどき「怖い」という感想が書き込まれている。
それを読んで考えたのだが、「真実」とは本来、「恐怖をおぼえる」ものなのではないだろうか。逆に言えば、知ることで「恐怖をおぼえる」ようなことこそが、本当の「真実」と言える。
今は情報が山盛りにあふれていて、簡単に何でも知っている気になれるけれど、その大半が、発信者の都合のよいようにスポ ...
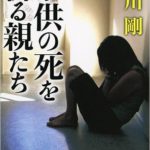
「子供の死を祈る親たち」二刷り増刷&コミックバンチ第四話掲載
子供の死を祈る親たち (新潮文庫)
posted with ヨメレバ押川 剛 新潮社 2017-03-01AmazonKindle楽天ブックス7net「子供の死を祈る親たち」が増刷(二刷り)されました。累計2万1千部。地味ながら頑張ってます!皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。
漫画版『「子供を殺してください」という親たち』は、コミックバンチwebにて、電子版の第四話が掲載されています。コメントも相変わらず芯食ったものが散見され、 ...

現代版わらしべ長者
現代にもわらしべ長者があるとすれば、それは“もの”の交換ではない。どこまでいっても“こころ”のやりとりである。そして、現代における“こころ”の最上級は、鮮度の高い、具体的解決策を伴う「情報」ではないか、という気がしている。
「情報なんて今やネットにいくらでもあふれてるじゃん」と思うかもしれないが、どの分野でも、本当にやばい肝のところほど、表に出さないし出せないし出てこない。それは、対面の、空間ではない現実のコミュニケーション、つまり“こころ”のやりとり ...

人脈しかない
以前、人間的・経済的、健康的にもゆたかに生きている方に、その秘訣を聞いたところ「人脈しかない」と返ってきた。その方のいう「人脈」とは、著名人や権力者とつながっているという意味ではない。純粋に、どれだけ「人」を大切にし、真剣に「人」と向き合ってきたか、ということだった。
「ただし」とその方は言った。「バカは相手にしない」と。だから俺は尋ねた。「私も大学中退のバカですけど、どうして相手をしてくれるのですか」。「押川さんはバカじゃないわよ。自分がバカだって分 ...

人生とは出会い
10年くらい前、信頼する精神科医のT先生が話してくれたこと。
『最近は、「子どものために自分の人生を犠牲にしたくない」ということを平気で言う親がいる。「人生とは出会い」であり、人生という容れ物のなかには出会いしか入っていない。よって、子どもとの出会いは人生にとっては一大事である』。
『しかし、その人生の現実を無視して、無意識のうちに自分が「快」だと思う方向に、自分にとって都合のいい屁理屈を述べ立てるような知的能力だ ...
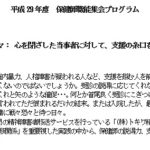
保健師さんに講演
6月になった! それにしても今年は暑い! このまま温暖化が進むと、2050年には魚が獲れなくなる(食べられなくなる)らしい。2050年まで生きているかは微妙だが、魚が食べられなくなるのは悲しいなあ。
さて、6月中旬には、新潟で講演の予定が入っている。新潟県看護協会主催「保健師職能集会プログラム」での講演だ。スタッフを通じてこの話を聞いたとき、俺は自分の耳を疑った。
なぜなら俺は、拙著『「子供を殺してください」という ...